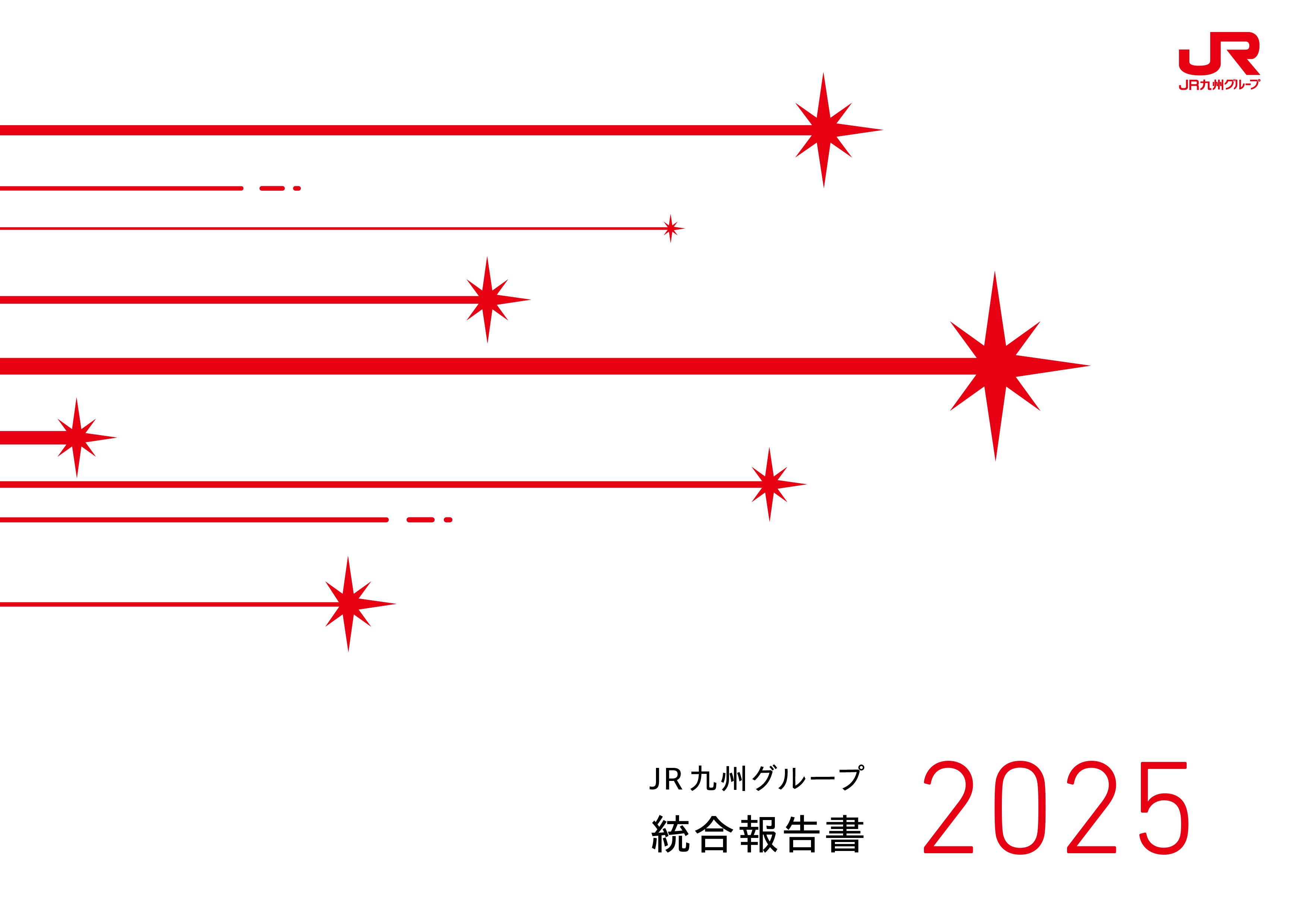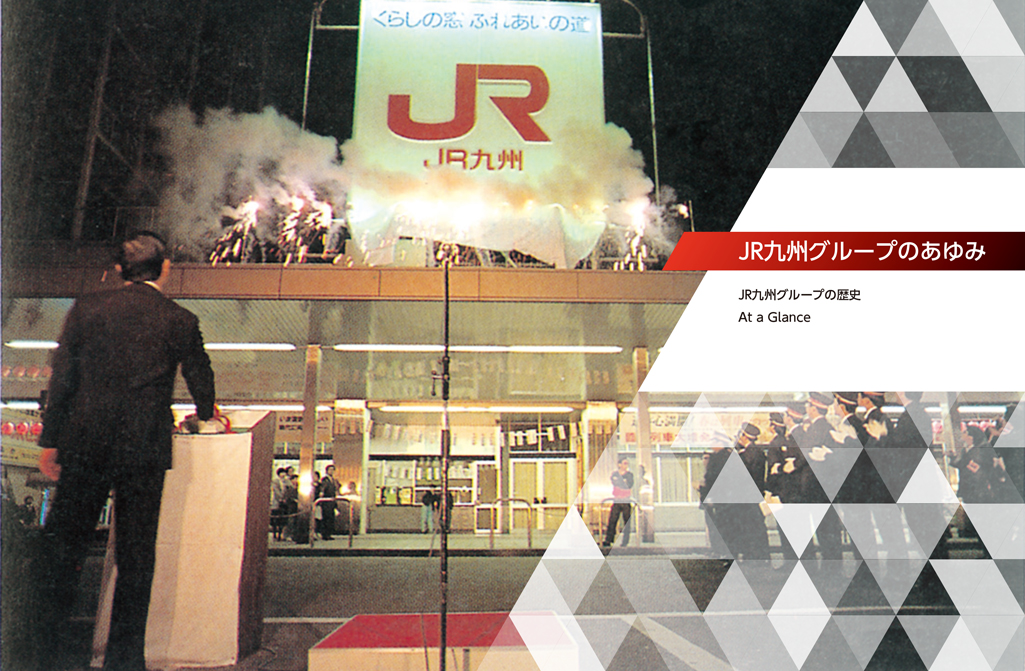社外取締役メッセージ

対話を通じて相互理解を促進
社外取締役を3年務めてきた中で、JR九州グループの安全や事業拡大に対する姿勢はANAグループのそれに近い印象を抱いており、自分の経験や知見を活かして当社グループの成長に貢献しようと努めてきました。取締役会の議論については、事業への理解を深めるための事業研修や議題に関する細やかな事前説明によって、当日は自由な発言を促す議長の雰囲気づくりもあり、質の高い闊達な意見交換が実現しています。
中期経営計画2025-2027についても作成の途上から取締役会で議論を重ねたことで、社外取締役としても自信を持って打ち出すことができたと考えています。今後、中期経営計画の進捗状況をモニタリングしていくにあたり、グループ会社に対しては、現場に赴き経営層や従業員と意見交換を重ねながら実態や課題を把握したいと考えています。
グループガバナンスの強化として、グループ各社に常勤監査役を配置することとしました。各社の企業文化を尊重しながらも、安全・安心をはじめとした当社グループとして大切にする理念を確実に浸透させるため、対話を通じて相互理解を促進し、必要に応じて改善を図っていくべきだと考えています。各社の監査役とも意見交換を進めながら、引き続き社外取締役としてJR九州グループの持続的な成長と健全なガバナンスの実現に貢献してまいります。


リスク感度の底上げを図る
2023年6月に社外取締役に就任してからの2年間、コロナ禍からの回復期において、グループ全体として着実な業績回復と中期経営計画の順調な進捗を見届けることができました。
一方で、高速船の事案を通じて、グループガバナンスやインシデント対応の仕組みには改善の余地があると痛感しました。取締役会において内部監査の頻度に関して意見したことがありましたが、今回の事象を契機としグループ会社の監査体制を見直すこととなったのは、仕組みの改善としては大きな進歩です。特に、心理的安全性の確保や、原理原則に基づいた判断を全社的に徹底することの重要性を再認識しています。多様なグループ会社においても、共通の価値観と仕組みを持ち、信頼される企業であり続けるために、今後も社外の視点を活かし、客観性と健全な緊張感を持って、ガバナンスの深化に貢献してまいります。
また、現場からの声が適切に吸い上げられ、リスクが共有される風土づくりが不可欠です。企業の成長に応じたガバナンスの進化を支えるべく、引き続き外部の立場から積極的に関与してまいります。グループ各社の特性を尊重しつつも、共通の原理原則を軸に、監査や情報共有の仕組みを整備し、リスク感度の底上げを図ることが、今後の持続的成長の鍵となります。これからも、信頼と誠実さを基盤に、社会から選ばれ続ける企業グループであるための一助となるべく努めてまいります。


「何を守り、何を変えるべきか」を見極める
当社グループの社外取締役として、企業文化の観点から果たすべき役割があると考えています。企業文化とガバナンスは密接に関係しており、ガバナンスが形式的に整っていても、企業文化がそれを支えるものでなければ、実効性は伴いません。不正を見つけても言い出せない雰囲気や、ルールを形だけ守る文化が根付いていると、どれだけ制度を整備しても組織の健全性は保てません。逆に、組織の風通しが良く告発や意見を出す人が不利益を被らない土壌が整っていればガバナンスの仕組みも有効に機能し、継続的な改善や変革が可能になります。
安川電機では製造業として変化の激しいグローバル市場の中で競争力を維持するため、企業文化も変化させてきました。また、ガバナンスは単なる監視ではなく、「何を守り、何を変えるべきか」を見極めることが重要だと考えます。製造業においてISOやTQM(総合的品質管理)で培ってきた「仕組みを見直し、絶えず改善を重ねていく」という精神は、当社グループのように高い公共性を担う企業においても、大きな意義を持つと考えています。今後も社外の視点を活かし、より開かれた企業文化と健全なガバナンスの進化に貢献してまいります。


鉄道以外においてもリスク管理の精度向上を
就任から1年が経過し、当社グループは活力に満ちており、オープンな組織であるという印象を抱いています。部長級や中堅社員など、様々な階層の社員との意見交換の機会があり、これらの交流を通じてオープンで活力がある風土が根付いていることを実感しています。
グループガバナンス強化の議論においてはリスク管理という観点から意見を述べてきました。リスクには「事業リスク」と「業務リスク」の二つがあり、理念に則しているのか、採算性はどうかという事業そのものに対する「事業リスク」と業務執行上における幅広い意味での「業務リスク」は異なるアプローチが必要です。特に業務リスクに関しては、鉄道を祖業とする歴史的な背景から、鉄道と鉄道以外のリスク管理の精度に違いがあるのではないかと感じています。鉄道に関しては日々の事象について情報が共有される仕組みが整備されています。それと同様に鉄道以外においても整備していく必要があり、そのリスク情報を共有することは良いことなのだという企業文化の醸成も併せて重要なことです。
今回の高速船の事象を契機にグループ全体の監査体制を強化しますが、その対策が十分に機能しているのか、執行の仕組みは適切なのかという視点を持ってモニタリングしていくことで社外取締役としての役割を果たしていきたいと考えています。
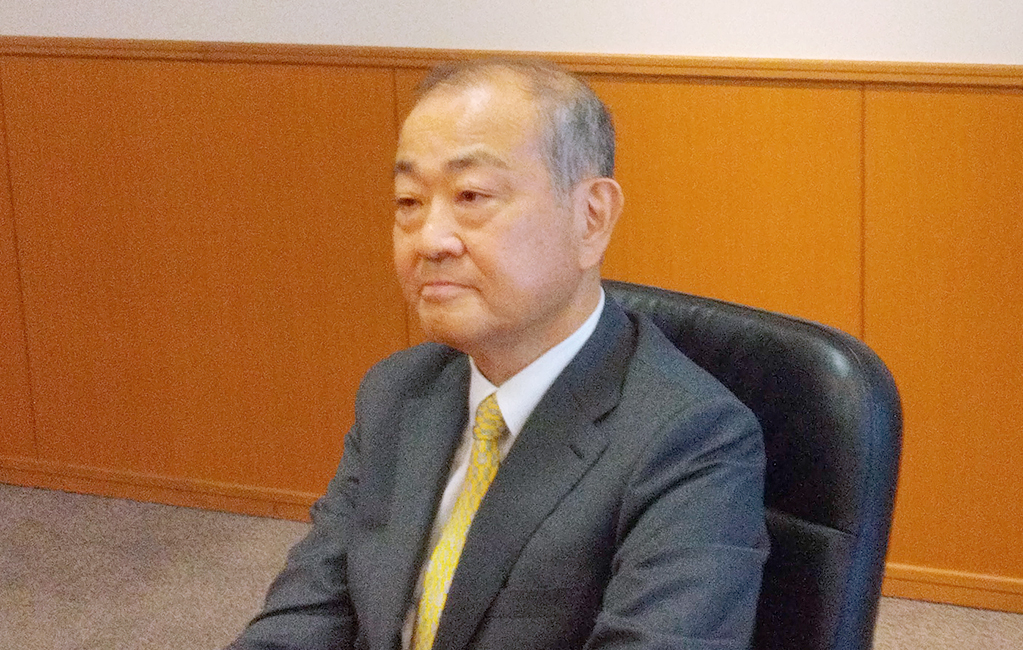

実効性のある真のDE&Iを目指して
昨年の就任以来、人材戦略については、取締役会だけでなく人事部門とも議論を重ねてきました。特に管理職の女性比率に関する従来のKPIを見直し、単に比率を追うのではなく、持続性のあるDE&I実現のために、女性社員の積極的採用によって管理職候補者の母数を増やし、定着を図ること、そして昇格の機会において不利にならない仕組みとすることを重視し、新しい目標を設定しました。これによって、より実効性と納得感のある内容になったと考えています。
一方で、DE&I推進の目的は女性に限らず、様々な事情を抱えるあらゆる社員が、力を発揮し、組織に貢献できる環境を整えることにあると考えます。現在は施策の第一歩として女性が対象となっていますが、それが最終目的ではないという点については、これまでも様々な議論の場で意見を述べてきました。
また、人的資本経営はリスクマネジメントの観点からも重要であるということを提言しています。優れた人材を確保し、ロイヤルティが高い状態が維持されている組織では、不適切な行動を起こすという動機そのものが生じにくくなると考えるからです。グループガバナンス体制強化の一環として、各社に常勤監査役を設置することとしています。監査役には、ロイヤルティの状態や、従業員としての誇りが保たれているかといった点も把握することを期待しています。取締役会はグループ監査が適切に機能していることを継続的にモニタリングしていきます。

Contents