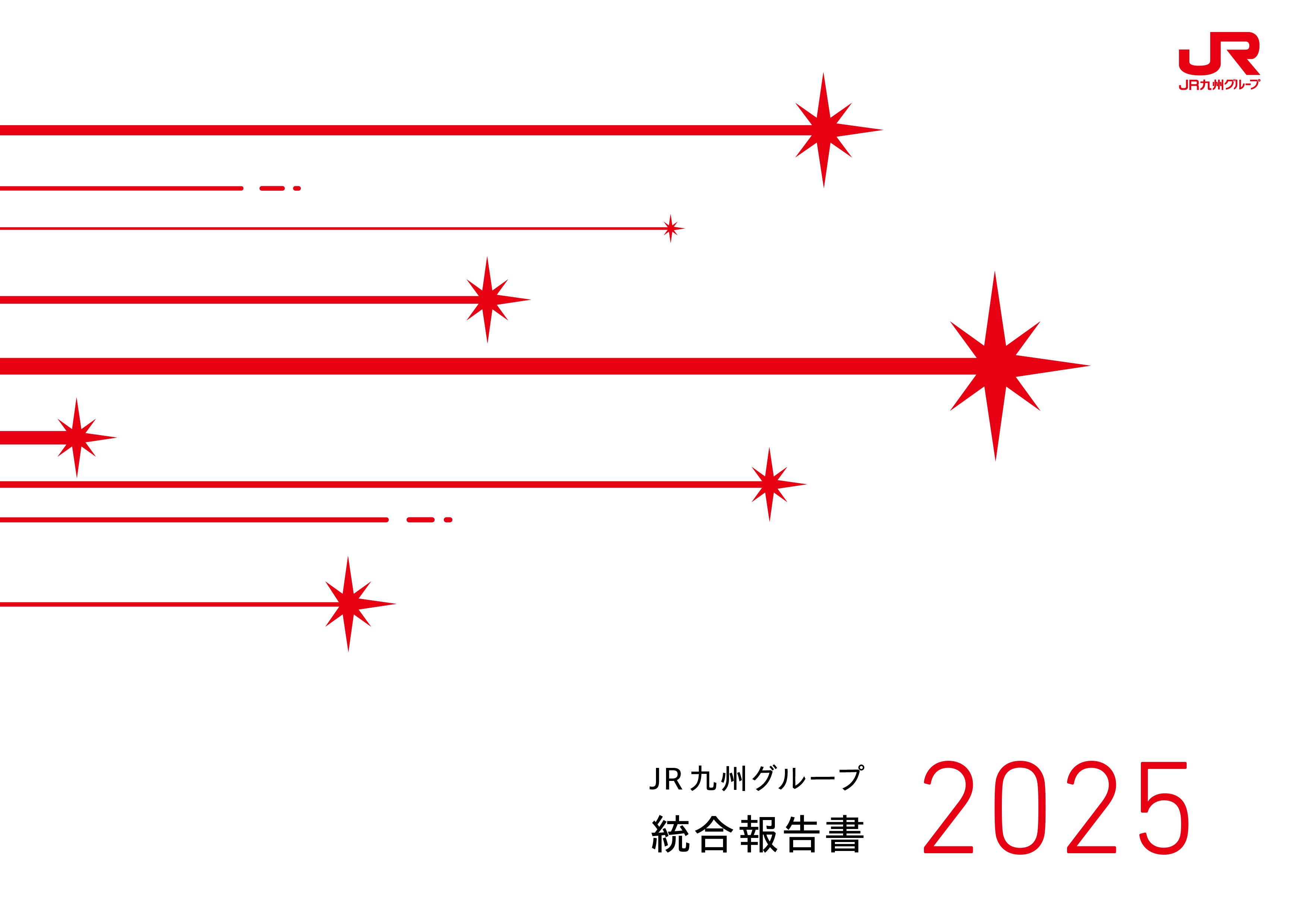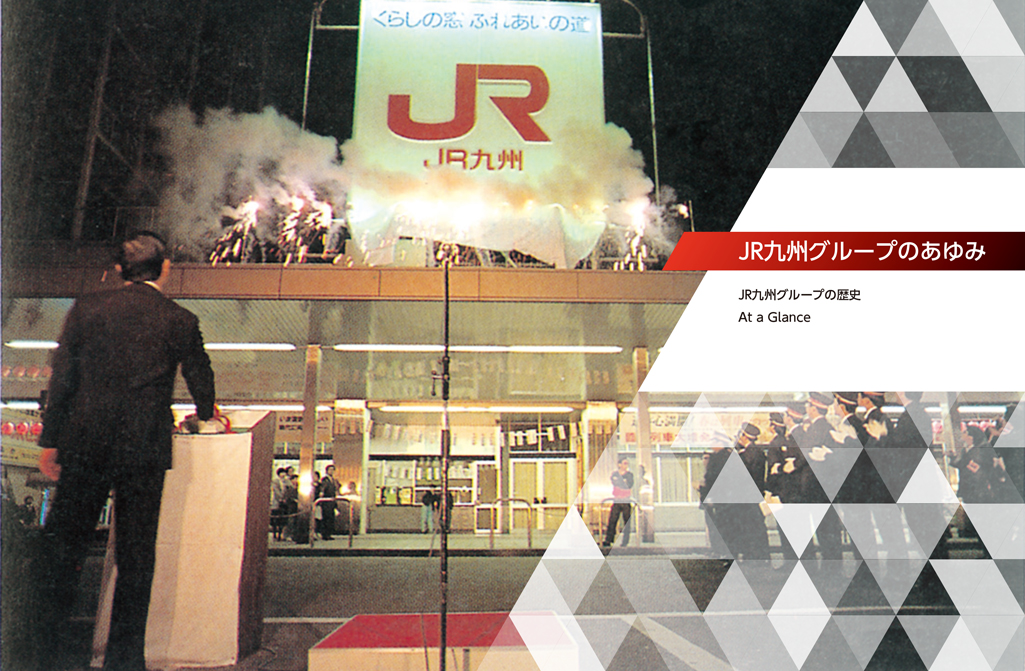CFOメッセージ

事業戦略と財務戦略の連動により
企業価値を拡大させていきます
取締役常務執行役員
最高財務責任者松下 琢磨
当社グループは新たな局面を迎えました。コロナ禍から成長軌道への復帰を果たし、“これからはどのような状況にあっても持続的な成長を果たしていかなければならない”、そんな局面です。上場企業であることの大きな意義は、成長することにあると考えています。どのような状況にあっても成長を希求し、中長期的な戦略のもと人を育て、既存事業の成長と変革、そして新たな事業に、常に挑戦していかなければなりません。
そのためには、成長への投資、人材への投資、株主還元の3つを、ともに成り立たせていく必要があります。まず未来に向けてサステナブルな成長を図るべく、リスクテイクをしながら成長投資を行うことが必要です。そしてそのためには、グループ全体を俯瞰しながら人材を確保し育てていかなければなりません。「個の力の最大化」によるグループのさらなる成長により、社員に対してより大きな投資を可能にする“好循環”が生まれていきます。同時に、株主の皆さまに中長期的にグループの成長を認識いただくとともに、安定的に還元を行っていく。
この3つをともに成り立たせていくべく、皆さまにお示ししたのが、今年3月に発表した中期経営計画です。
中期経営計画を実行していくのは社員です。社員一人ひとりが「やるぞ」という気持ちにならなければ達成はできません。そこで今回、新たな局面を迎えたことを踏まえ、新たな経営理念を策定しました。これをしっかりと浸透させていくべく、本社や現場の一人ひとりに向けて説明会を実施しています。
また理念策定と併せて、当社グループが常に考えるべき「マテリアリティ」を再考しました。これまで掲げていた「2030年長期ビジョン」を発展的に解消あるいは昇華させ、事業面と基盤面で整理しました。長期的なマテリアリティの視点に立ち、この3年間は具体的に何に取り組むのか、ということを定めたものが中期経営計画です。

バランスシートマネジメントが不可欠
今回の中期経営計画では、バランスシート構築の考え方を初めて開示しました。事業戦略と財務戦略の連動を常に意識し、ROEの維持向上を推進するなど、資本効率性及びレバレッジを意識したバランスシート構築を進めていきます。
事業戦略:鉄道事業
~29年ぶりの運賃改定を安全・人材投資の原資に
事業戦略の柱として、「既存事業の成長・効率性向上」を掲げました。鉄道事業では、今年4月1日に29年ぶりとなる運賃・料金の改定を実施しました。国が定める運賃改定のガイドラインの改正が行われたのを受けて、他社に先駆けてスピーディーに申請に踏み切りました。今後運賃改定に加え、様々な施策によるトップラインのさらなる向上とともに、設備のスリム化やコロナ禍で実施したBPR(Business Process Re-engineering)以降継続してきたコスト削減、新技術導入等による省人化、省力化に取り組むことにより、鉄道事業の基盤をさらに強固にしていきます。
すでに前中計期間において、新たに「未来鉄道プロジェクト」をスタートさせています。以前のBPRは「コスト削減」の視点で進めてきましたが、この未来鉄道プロジェクトでは収支改善に資する投資も躊躇せず行い、コスト削減とトップラインの向上による「収支改善」の視点で進めていきます。プロジェクトがスタートした2022年度から2030年度までの間で「収支改善額140億円」を目標としており、社員の一人ひとりの意欲的な取り組みにより、すでに効果も発現しています。社員が鉄道の未来を自ら描き行動していくことで、社員の意欲向上にもつながり、収支改善が進んでいくと確信しています。
事業戦略:不動産・ホテル事業
続いて不動産・ホテル事業です。現中計の期間は、今ではまちのランドマークに成長を遂げた駅・駅ビルを核に、その周囲にオフィスや都心型レジデンスなど成長分野の拡大を進め、まちのにぎわいをさらに拡大していきます。またインフレ下にある市場環境において、賃料収入の拡大に貪欲に取り組み、内部成長を図っていきます。
ホテル事業においては、従来から取り組んできた稼働率やADRの向上に努めることはもちろん、福岡市において当社グループでは4件目となる、新たなホテルの開業を2028年度に予定しています。従来から進めてきたアセットライトによりホテル事業を強化しようというもので、今後も基本的にこの方針でホテル事業の拡大を目指していきます。
加えて前中計期間以降取り組んできた、物流不動産事業の開発も進めます。九州においては、物流不動産の空室はまだまだ少なく需要は逼迫しています。自社単独での開発のみならず、他社と共同での開発にも取り組み、需要を取り込んでいきます。
不動産・ホテル事業の成長にあたって、最重要戦略の一つが「資産の回転」です。前中計期間において当社出資の私募リートに加えて第三者への資産売却を進めてきましたが、現中計でも資産回転を着実に進め、開発利益とマネジメント収益を拡大させることにより、資産効率性を意識した事業展開を行います。
事業戦略
~適時適切な事業等の見直し
事業戦略のもう一つの柱が「適時適切な事業等の見直し」です。これまでも“事業ポートフォリオに完成形はない”との認識のもと、撤退を含めて事業ポートフォリオを見直してきました。例えばドラッグストア事業、リース事業、ベーカリー事業、船舶事業等です。同時に新たな成長を目指し、積極果敢にM&Aも行ってきました。適時適切な事業の見直しは、当社が歩んできた“歴史”でもあります。
また政策保有株式についても縮減に取り組んでいきます。これまでも保有目的を踏まえ、定性面・定量面から保有の適
否を判断し、保有の必要性が乏しい銘柄については売却を
行ってきましたが、その判断の目線あるいはハードルをさらに
上げ、保有の適否を判断していきたいと考えています。
バランスシート構築の考え方

事業戦略
~九州の元気を取り込む
事業戦略を描くにあたって大切なことは、九州の元気をしっかりと取り込んでいくことだと考えています。九州には半導体をはじめとした大きな投資の波が来ています。また、インバウンドの方々の来訪という波も来ています。そうした中で九州には“日本一元気なまち”とも言われる福岡都市圏や、台湾のTSMCの工場が進出した熊本都市圏など、大きな成長ドライバーがあります。
福岡都市圏における鹿児島本線や篠栗線、熊本都市圏における豊肥本線において鉄道の機能強化を図ることで地域のポテンシャルを上げると同時に、沿線での不動産開発事業などの検討を進めていきます。当社が手掛けた特徴あるまちとまちが交通ネットワークで結ばれることにより、九州内の移動を生み出し、元気な九州づくりを当社が牽引していきます。
また日本はインフレ下にあります。これは様々なコストの上昇圧力と言う意味ではピンチでもありますが、お客さまに選ばれる商品や価値を提供し、適切な価格設定を行い、トップラインを上昇させることができる機会とも言えます。この波をしっかりと取り込んでいくことも大切だと考えています。
当社グループにおける各事業が自立・自律した成長を確実なものにしたうえで、さらに事業間で連携を強め、JR九州グループの「コングロマリット・プレミアム」を最大化していきます。そのためにも、今年4月にはデータ活用やマーケティングの強化を目的に「未来市場戦略部」を新設し、当社グループをご利用のお客さまの特性や行動の把握を進めるとともに、新規のお客さまの獲得などを目指して取り組んでいます。
財務戦略
~レバレッジの活用により前中計を上回る投資を着実に実行
財務戦略に目を転じます。当社のバランスシートコントロールにおいて大切なポイントは「負債の活用」です。借入や社債などによる調達においては、レバレッジをさらに効かせ、現中計期間中は営業キャッシュフローを超える成長投資を実行していきます。上昇局面にある金利負担に目配りをする必要はありますが、当社のデットキャパシティは十分にあります。前中計期間はコロナ禍ということもあり、D/EBITDA倍率や自己資本比率の水準を目安あるいは規律として定めていましたが、現中計の局面においては、デットキャパシティを柔軟にコントロールできる力があると考えています。
また、「自己資本のコントロール」も重要です。持続可能性を意識し、適正な水準でレバレッジをコントロールするとともに、収益の向上を通じた配当金の増加や機動的な自己株式の取得により、積み上がる自己資本を適切にコントロールしていきます。
安全の確保を前提とし、交通インフラを担う企業グループとして、バランスシートマネジメントは持続可能性の担保を意識した長期視点での経営を行い、地域を牽引していくための基盤だと考えています。

バランスシート構築のための
キャッシュアロケーション
キャッシュイン、キャッシュアウト
現中計の3カ年におけるキャッシュインとして、まず営業キャッシュフローを2,500億円と見込んでいます。運賃・料金の改定をはじめとした施策によりトップラインのさらなる向上に取り組むとともに、様々な上昇圧力がある中でもコストの削減に取り組み、前中計を上回る営業キャッシュフローを生み出していきます。またその中で、不動産物件売却によるキャッシュインを約300億円見込んでいます。豊富な成長機会のある九州ですので、成長投資の機会は多くあり、キャッシュアウトが増加することも想定されますが、社債や借入等によるキャッシュインについては、前述した通り、当社のデットキャパシティは十分にあることから、レバレッジをかけていくことができると考えています。
キャッシュアウトですが、まず設備投資の総額は3,600億円を予定しており、営業キャッシュフローを活用して前中計を上回る1,300億円の維持更新投資(安全投資を含む)を行い、鉄道の持続可能性を高めていくとともに、長期安定的な配当の実現を目指して、株主還元の拡大を図っていきます。また営業キャッシュフローと財務キャッシュフローにより、2,300億円の成長投資を実行していきます。現時点で成長投資には未確定分が約900億円あります。今後、物流不動産事業の拡大、将来の再開発の“種”としての収益不動産の取得、あるいは大型のまちづくり等での活用を想定しており、当社の豊富なネットワークを活かし、取り組みを進めていきます。未確定の額は前中計のスタート時点においても同額でしたが、3カ年で計画通り遂行することができ、主に不動産・ホテルセグメントの成長に寄与していますので、現中計でも計画通り遂行することができると考えています。
キャッシュアロケーション

「戦略投資」の新設と規律ある投資判断
現中計の大きなポイントの一つが、「戦略投資」を新設したことです。成長投資に加えて、柔軟かつ機動的な使途に応える枠組みで、M&Aなどに活用する想定です。M&Aの領域は限定していませんが、JR九州グループの第三の柱となる事業、あるいはグループ総合力を活かせるBtoB、BtoG分野の強化等を念頭に検討しています。他の戦略投資の使途としては、将来の成長に向けた不動産事業等での成長投資の積み増しも念頭にありますし、逆に投資機会に恵まれなければ自己資本のコントロール等の観点から株主還元に充当することも選択肢として認識しています。
当然、戦略投資や成長投資を実行する際は、規律ある投資判断を行う必要があります。企業価値を向上させていくためには、グループ全体で守るべき統一した投資判断基準を設定し、株主の皆さまが期待する以上の収益性を維持していくことが必要だと考えています。ハードルレートを常に認識し、市中における利回り水準に加えて定性的な効果も含めて判断し、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいきます。

数値目標及び株主還元方針
財務KPI
~ROEと資本コストのスプレッドが企業価値の源泉
現中計では「営業収益5,300億円」「営業利益710億円」「EBITDA1,150億円」の財務KPIを掲げました。様々な厳しい経営環境を踏まえた場合、決してやさしい数値ではありませんが、全社員が力を合わせて取り組むことで達成可能だと考えています。
また、ROEについては「現行水準の維持」を目指していきます。当社の場合、株式上場時の鉄道事業の固定資産の減損により、その後の設備投資に伴う減価償却費が毎年増加していきます。また成長力の源泉となる人材確保へ向けて、ここ3カ年でも約20%の賃上げを行ってきましたが、今後もさらに一定程度賃上げを行っていく必要があると考えています。加えてインフレによる物価高騰や設備の老朽化対策など、ROEの下方圧力が顕在化しています。こうした環境下においてもROEを維持あるいは向上させていこうという考えです。
そして最も大切なことは、ROEと資本コストとのスプレッドを拡大していく取り組みだと考えています。現状の資本コストはCAPMや株価収益率、また投資家の皆さまとの対話などから考えた場合、5%半ばから7%半ばの水準と認識していますが、これを引き下げる努力を続け、スプレッドを拡大することで企業価値の拡大を目指していきます。

配当性向の「下限」撤廃。
配当額の増加とともに自己株式取得を機動的に行う
株主還元を長期安定的に行っていくことは、当社の最重要施策の一つです。前中計では、下限を設けコロナ禍の中でも高い配当性向で安定的な還元を行ってきました。現中計では、これまでの「1株当たり93円を下限とし、配当性向35%を目安」という方針から、下限を撤廃し「配当性向35%以上」と還元方針を定めました。下限を撤廃したことは配当額を下げることを企図したものではなく、利益の伸長に合わせて配当金を増額していくつもりです。
また自己株式の取得については、100億円の規模で今年5月に実施しました。もともと、前中計の還元方針において「機動的に自己株式の取得を検討する」としていましたが、これに基づいて今回、前中計の3カ年の取り組みを振り返り、前中計策定時点と比べ、キャッシュフローの上振れや自己資本比率の上昇等があると認識し、同時にステークホルダー間のバランスや株価水準等、総合的に勘案した結果、実施したものです。
現中計期間においても、株価の状況、キャッシュフローの状況や資本効率の状況、成長投資や戦略投資の見通し、ステークホルダー間のバランス等を見ながら機動的に判断していきたいと考えています。言うまでもないことですが、今後の自己株式取得は常に「中計の結果を受けて判断する」というものではありません。前述の状況を把握し、適時適切に機動的な判断をしていきます。これらの現中計の還元方針は、前中計に比べ還元強化の段階を1レベル、2レベル引き上げたと考えています。

企業価値向上につながる非財務KPI
実効性のある非財務KPIの設定により
企業価値向上を図る
まずグループガバナンスは、当社にとって最も重要な経営基盤だと考えています。昨年当社子会社であるJR九州高速船㈱が起こした問題を重く受け止め、ガバナンス強化に向けてしっかりと取り組んでいきます。改善施策については、すでに様々な場面でお示しをしていますが、風通し良く何でも言い合える風土づくりと仕組みづくりを進め、安全を最優先に考える意識をグループ全体にしっかりと浸透させていきたいと考えています。
沿線人口の増大をまちづくりのKPIに
「まちづくり」関連のKPIでは「沿線人口」を新たに加え、当社の鉄道沿線の人口減少率が九州全体の減少率を下回ることと定めました。沿線に「住みたい・働きたい・訪れたい」と思えるまちづくりを進め、まちとまちを交通ネットワークでしっかりつなぎ、移動を生み出すことが大切だと認識しています。交流人口や雇用が生まれれば、最終的には沿線に定住する人口が増え、九州が元気になっていくと考えています。
人材戦略はより実効性のあるKPIに
価値創造の源泉である人づくりの面では、ジェンダーダイバーシティのKPIをより実効性のあるものに改めました。「女性管理職を全管理職の10%以上」としていた前中計でのKPIを改め、管理職比率だけではなく、採用・定着・登用の3つの観点で新たにKPIを設定しました。
国鉄から発足した当社の歴史を振り返ると、長年女性社員が極端に少ない社員構成が続いていました。このため、管理職に登用されるタイミングを迎えた女性社員の数を考えると、「女性管理職10%以上」という目標は、逆に歪んだキャリアパスを引き起こしてしまう可能性がありました。そこで、まず母数となる新入社員の女性割合を毎年30%以上とし、女性の定着率を重視したうえで、登用にあたっては勤続15年以上の社員(退職しなければ勤続15年に達した者を含む)に占める女性管理職の割合が男性管理職を下回らないとする、という目標を掲げました。
このために今後、社員が離職の道を選ばず、長く働ける環境を整備すべく、勤務制度やメンタル的なサポートの充実など、様々な施策を実行していきます。当社は様々なお客さまにご利用いただいていることから、JR九州グループ全体で「DE&I」を進めていくことは、今後の競争力向上に不可欠であり、企業価値向上の最重要テーマの一つだと考えています。
さらなるエンゲージメント向上を目的とした
従業員意識調査へ
従業員意識調査については、調査結果(総合満足度)が毎年前年度を上回ることを現中計でのKPIとして設定しましたが、従業員の一層のエンゲージメント向上を企図し、利用ツールの見直しに着手します。今後は、調査結果を多くの国内企業や業界他社の結果とタイムリーに比較することで、当社グループのポジショニングを把握し、具体的な施策に活かせるものにしていきます。また、従業員の属性や採用区分などによるクロス分析や、期待と満足の2つの軸による効果的な打ち手の検討も行います。現業機関などの職場単位において、自らが自職場の問題や課題を抽出し、エンゲージメント向上へスピード感を持って取り組んでいきます。
地球環境に向き合う姿勢を示す
「JR九州グループ環境ビジョン2050」を策定
環境分野では、気候変動をはじめ、資源循環や生物多様性といった課題に長期的に対応するため、当社グループの姿勢と目指す姿を示した「JR九州グループ環境ビジョン2050」を今年2月に策定いたしました。その中で、2035年度までにGHG排出量60%削減という意欲的な目標を掲げるとともに、サプライチェーン全体の排出に関わる「スコープ3」についても、現中期経営計画の期間内に数値目標を設定し、段階的に取り組んでまいります。また、GHG削減にとどまらず、資源循環や生物多様性の維持にも目を向け、当社としての重点分野を定めたうえで、方針を明確にしました。これらの取り組みは、経済性との調和を図りながら着実に進めていくものであります。この姿勢が、企業価値の向上にとって重要な要素であると認識しております。


ステークホルダーの皆さまへ
皆さまとの対話を深め、
JR九州グループの力と可能性を発信していきます
私は当社の企業価値は現状の評価よりも高いと自負しており、現在の株価水準にも満足しているわけではありません。
コロナ禍において鉄道事業の固定費削減を機敏に着手し実現させ、同業他社よりも早く黒字回復をすることができました。価格戦略については会社発足以来の厳しい経営環境が逆に価格への感度を高めるとともに、運賃・料金の改定にもいち早く取り組みました。また、鉄道のローカル線に関する収支状況をいち早く開示し、実情を共有させていただき、現在地元の皆さまとの協議にも精力的に取り組んでいます。当社がこれまで築いてきた地域との良好な関係性を活かすとともに、BRTなどの様々なモデルをお示しすることが可能です。
前述しましたが、財務における信用力を背景としたデットキャパシティも十分にあり、当社の資本コストを低減させ、スプレッドを拡大することは十分に可能だと考えています。
当社では、IRやSR活動は今後の経営に資する様々なご意見を頂戴する貴重な機会であると考えており、“質、量両面での充実”を図ってきました。2024年度は機関投資家やアナリストの皆さまとの面談を数多く実施し、このうちの半分をCEOまたはCFOが出席し対話をさせていただきました。また、JR九州高速船㈱の重大な問題に対して、多くのご意見やご指導をいただき、改善策に活かしてまいりました。IRやSR活動において頂戴したご意見は基本的にすべて取締役会にフィードバックし、改善策に活かしています。
今後CFOとして、九州経済の成長のポテンシャルを活かしながら、変化に機敏に対応し、当社の短期と中長期の目標達成を両立させることで、これまで以上にJR九州グループの企業価値をご理解いただく努力を積み重ねてまいります。
Contents