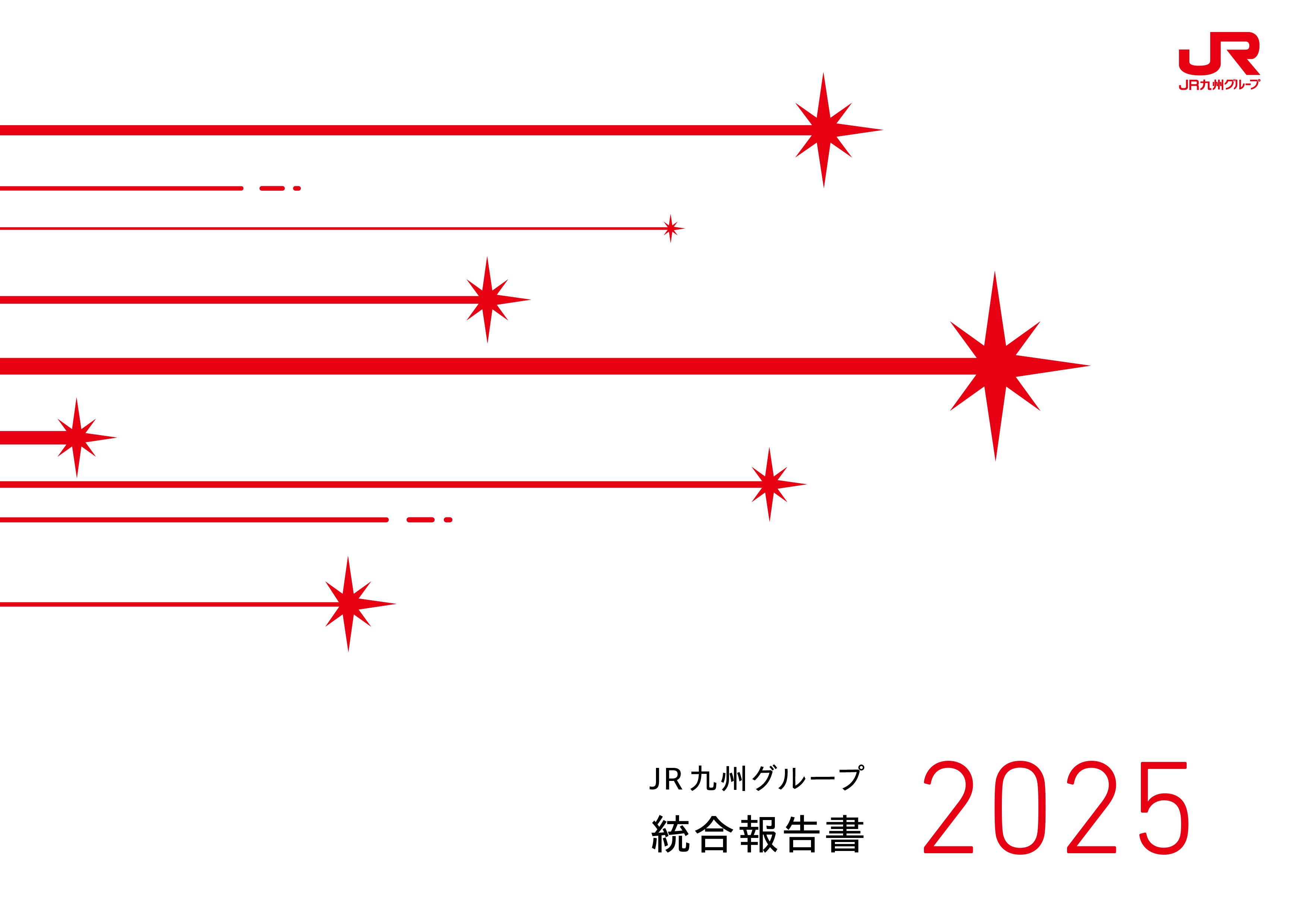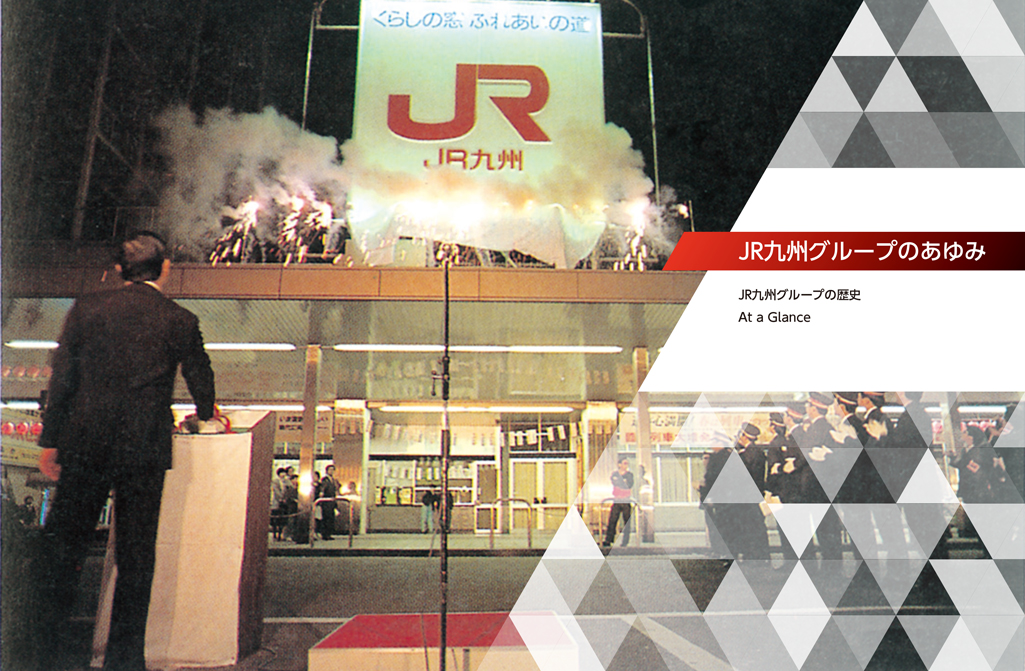トップメッセージ

わたしたちの夢は
「九州の元気を、世界へ」
代表取締役社長執行役員古宮 洋二
前中期経営計画ではコロナ禍から成長軌道への復帰を果たすことを目標としていました。この目標を達成した今、未来に向けて再出発するという意味を込めて、2025年3月に経営理念を一新しました。もう一段、高いフェーズでの成長を実現させるため、新たな理念のもとに全社員が心を一つにする必要があると感じたからです。一つ一つの言葉に込めた念い(おもい)をご説明したうえで、当社グループの今と未来についてお話しいたします。

経営理念の刷新に込めた念い(おもい)
「わたしたちの夢」
長年掲げてきた経営理念である「あるべき姿」という言葉を「わたしたちの夢」と改めました。「パーパス」よりも、社員にとってのわかりやすさを重視し、「将来に向けて、JR九州はこうなっていきたい」という意欲を表現するには「夢」という言葉で素直に表現する方がしっくりきます。その夢とは「九州の元気を、世界へ」です。「あるべき姿」では「九州、日本、そしてアジアの元気をつくる企業グループ」と表現していました。
「世界」としたのは、当社グループが展開するホテルに置かれた世界地図がきっかけでした。世界地図はお客さまがどこからいらっしゃったかをシールで貼ってもらうために設置したものですが、数えると70以上の国・地域の方にご利用いただいていました。当社のシンボル的な存在となったクルーズトレイン「ななつ星in九州」の利用者は40カ国。九州域内のフリーパスの利用者は95カ国。こんなに九州と世界が強くつながっているとは驚きでした。
実際に「ななつ星in九州」をご利用になったお客さまは「沿線の方々のおもてなしが良かった」と話されます。九州という地域の「おもてなし」が世界中を元気にしているわけです。そして、当社の社員の得意技も「元気」。よく社外の方から「とにかくJR九州の人は元気だね」と褒めていただきます。九州という地域の笑顔や温もりを、元気が取り柄のJR九州グループの社員が世界の方々に届けている。「元気がなくなったら、また九州においでください」と九州を代表して言いたい。そんな「念い」を「夢」に込めました。
「使命」
夢を形にするための当社グループの「使命」を定めました。これまで「安全とサービスを基盤として」と表現してきたのですが、鉄道部門に従事する社員から「なぜ、安全とサービスが並列なのか、安全こそ最大の使命では」という意見が出ました。議論当時、高速船での事象が顕在化した時期でもあり、「安全があるからお客さまに満足していただけるサービスを提供できる」との考えを新たにしました。そこで「安全を最優先し」と最初に明言しました。そのうえで「私たちの役割とは何か」を議論し直しました。
当社グループがお客さまに提供すべき価値は、通勤通学など定時で移動できる「当たり前の日常」と、「一生一度の旅」や「ハレの日」など特別なシーンを彩る「感動の非日常」だと考え、この日常と非日常をつくることが我々の使命であり、この2つの使命を「安心で快適な毎日」「“わくわく”するとき」と表現しました。
「おこない」
使命を全うするための「おこない」については、これまでの「誠実」「成長と進化」「地域を元気に」の3つのうち、「誠実」を残しました。ごまかしのない、うそのない対応で安全と向き合い、さらに様々な事業を進めるために最も大事なことは「誠実」であるという考えに変わりはありません。残りの2つは「共創」「挑戦」です。私はコロナ禍の苦しい時も「成功の反対は失敗ではない。何もしないことだ」と社員に言い続けてきました。その「念い」はこれからも変わりません。そして当社グループの未来は、地域の方々や企業、自治体などとの「共創」なしに語れません。

経営理念に手を入れる企業は、あまりないのかもしれません。決して言葉遊びをしているわけではありません。時代や価値観が変化すれば、社員やステークホルダーの皆さまに理解しやすい最適な表現を探す。社員と改めて理念について語り合ってみて、ポストコロナ時代における本当の意味での成長を目指す当社グループにとって、この対話は必要なプロセスだったと確信しています。現在も社員一人ひとりの心に浸透するよう、社員との対話に力を入れています。

中期経営計画2022-2024を振り返って
人流に依存しない「第三の柱」に課題残す
2024年度に終了したJR九州グループ中期経営計画2022-2024(以下、前中計)を振り返りますと、鉄道事業の固定費削減で着実に成果を出すなど、社員の頑張りを数字として表すことができた3年間だったと評価しています。一つ心残りなのは「第三の柱」と呼べる事業を育てられなかったことです。コロナ禍には「人流」が止まり、鉄道利用者の減少、駅ビル利用者の減少と、駅関連のビジネスが停止してしまいました。マンション事業等の不動産事業は好調に推移しましたが、今後も不動産市況が安定し事業拡大が続くという保証はありません。人流に頼らない事業ポートフォリオを構築するためにも、新たな事業の柱をつくっていきたかったのですが、次期に持ち越す結果となりました。
高速船問題の本質はグループ間の人事交流不足
何よりも深刻な問題は、JR九州高速船株式会社における安全確保に関わる重大な問題の発生についてです。2023年に船への最初の浸水の発生を確認し、国へ報告していました。当時、高速船事業会社の社長と私は何度も話し合い、国の指導も受けながら対策を決めて、その後の対応は同事業会社に託しました。振り返れば、この時の判断が私の反省点です。当初は「現場から安全対策に関する意見が言いやすくなった」と報告を受け、改善に向かっていると信じていました。しかし、同事業会社では、断続的に発生した船への浸水に対し徐々に「これくらいは大丈夫」と慢心が生まれ、「異常なし」として浸水を隠し続けていた状況に陥っていました。
この状況の発覚後、すぐに鉄道事業の安全管理を担当する「安全創造部」のメンバーを高速船事業会社に派遣し、徹底的に事実関係を調べました。一方で第三者委員会を設置し、客観的な立場で調査してもらいました。同委員会には同時並行で自社調査と改善策を進めることに承諾を得て、社員教育などの詳細を詰め、さらにはグループ内の他の業種のリスク管理体制も見直しました。
第三者委員会のメンバーから発せられた「同質性」という言葉が、今も私の心に深く刺さっています。高速船事業会社も当然、安全対策に力を入れてきました。しかし、それは「その道のプロ」たち“だけ”で考えた対策でした。今回の件を契機に非常勤の監査役から専門の常勤監査役を配置することとしました。同質ではない外部の目を入れる仕組みとしていきます。高速船に携わる人材は船員として育った「同質」の人材でした。異なる視点で議論できる環境ではなかった。グループ間の人事交流を進めてこなかった経営トップとしての責任は重いと、深く反省しています。
グループ全体のリスク管理を抜本見直し
グループ全体でのリスク管理体制を見直すにあたり、私が一番課題であると感じた点は、情報共有が徹底できていないことでした。例えば、ある駅ビルで発覚した設備の不具合が、他の駅ビルで後に顕在化する。業種ごとに専門的なチェックができる人材を常駐させ、グループ内のリスク管理を徹底する必要性を強く感じました。
例えば、「食の安全」に関連するグループ会社など、その分野に専属の監査役を配置したり、すべてのグループ会社に監査専属の人員を配置したりしました。これまで小規模の企業の監査役監査は兼務で行っており、モニタリングが不十分でした。当社グループは多くの業態を持つコングロマリットである以上、関連業界の法規制をしっかり学び、常時モニタリングできる監査体制が必要です。個々の現場の対応は事業会社を信じて任せ、親会社が手厚くサポートする。その形を短期間で、前中計期間中に体制整備できたことには満足していますが、これからはしっかり機能させていかなければなりません。

中期経営計画2025-2027
サステナブルなモビリティサービスの実現
今年4月、29年ぶりの鉄道事業の運賃改定を実施しました。
インフレ傾向が強まる中、資材の高騰で老朽施設等の修繕コストもかさみます。社員の待遇改善等による人材の確保も必要です。その中でも災害対応を含めた安全への投資に力を入れなくてはなりません。運賃改定はお客さまへの負担を増やすことですから、無駄にすることなく安全・安心で快適なモビリティサービスを創り上げていきます。
能動的なまちづくり展開
企業価値向上に向けた事業戦略も、現中計の3年間で大きく推し進めなくてはなりません。
マテリアリティの一つとして掲げた「まちづくり」について、この3年間は前中計にあった西九州新幹線に関連した長崎エリアでの開発など、大きなプロジェクトはありませんが、例えば、福岡市近郊の粕屋町や篠栗町と昨年包括連携協定を結び、新たな沿線価値向上について検討を進めているところです。自治体と連携して魅力あるまちづくりを積極的に進めます。
まちづくりには、鉄道だけでなく、不動産開発や建設、流通・外食など、あらゆる事業分野のノウハウが必要です。これまでは「縦割り」の意識が強く、グループ内の事業間で連携するケースが多くはありませんでした。今後は事業の掛け合わせで、新たな需要を創出していきます。
半導体産業の投資が集中し、大きな経済のうねりとなっている熊本でも、グループを挙げたまちづくりに挑戦していきます。先日、台湾の半導体メーカーTSMCが出資する、熊本のJASMのトップと直接お会いし「渋滞が深刻な状態になっている」などの意見をいただきました。それほど人、モノの動きが活発になっているわけで、鉄道事業者としての存在意義が試される状況でもあります。工場のある菊陽町に建設予定の新駅を中心に、暮らし・商業・文化それぞれの空間を整備する大規模プロジェクトが始動し、当社グループも参画しています。
「第三の柱」候補を数多く育てる
地域の道路などのインフラの管理・整備も、鉄道で培った地域との協力関係が活きてきます。例えば、北九州市とは跨線道路橋の包括的維持管理に関する協定を結びました。こうしたBtoGあるいはBtoB事業は、引き続き強化していきます。
不動産事業である物流倉庫などの需要の拡大も「第三の柱」の有力候補です。今後も半導体関連産業の九州進出は続くと予想されます。一方で、物流業界は深刻な人手不足に直面しています。こうした半導体の盛り上がりと物流業界の「2024年問題」で、在庫を留め置く物流拠点の不足も顕在化していきます。すでに不動産事業で物流関連の強化を進め、一定の比率を占めていますが、さらなる拡大を図ります。

サステナブルな経営を目指して
人的資本経営の推進
企業価値向上に向けた事業戦略を遂行するためには、人材の確保が大きな課題です。コロナ禍においては、残念ながら会社を去る社員が増えました。40歳以下の離職率が3%程度と、それまでの3倍に高まっていました。私は3年前に社長に就任して以降、人事給与制度の見直しを最優先で進めました。結果的に離職率は1%台に戻りましたが、今年4月にも大幅に給与引き上げを実施しました。現中計期間中でも計画的に制度の改革を進めていきます。
私は社員全員が定年退職まで働きたいと思える会社にしていきたいと思っていますが、そのためには仕事のやりがい創出が一番だと思っています。例えば真夏の炎天下での力仕事は極力機械化し、判断業務などやりがいを感じられる仕事にシフトさせていくことで採用における好循環が生まれると考えています。加えて、給与を上げていかなくてはならないと思っていますが、給与を上げると同時にマルチスキル化も必要だということを社員との対話の場では伝えています。例えば駅員と車掌といった、複数職種の業務スキルを持つ社員が増えることで、子供の発熱などの理由で急遽休みが必要となった社員がいた場合に、規模が小さな職場でも周辺の職場同士で調整することで、勤務の融通を利かせられるようにしていく。これは社員のやりがいにつながっていくものと思っていますし、そのマルチスキル化への対価として給与を上げていく、そういった納得感のある給与体系にしていきたいと思っています。
これまで社員との対話を大事にしてきました。社員の素直な意見が交わされる対話を重ね、「働く環境が良くなってきた」という社員の声が聞こえてくるようになってきました。従業員意識調査の結果からも、対話を重視し改善につなげていくというこれまでの方針は間違っていなかったのだと思っています。社員にとって何が望ましいのか把握するためにも、効果的なエンゲージメントを進めていきたいと思っています。
コロナ禍で醸成した「前例を打ち破る力」
鉄道事業では現在、「未来鉄道プロジェクト」を推進しています。これは、どんな時代にも対応できるサステナブルなモビリティサービスを目指した挑戦です。私は目指すべき方向性をわかりやすく示すため、「設備と資格を軽くする」と社内に指示を出しています。
「設備」については例えば、運行体系の変更により在来線の設備に余剰が生まれています。信号機を減らせば、信号を結ぶケーブルを短縮でき、保守点検コストも抑制できます。これは全国のJRグループでも初の試みで、様々な方面から興味を示していただいています。
「資格を軽くする」取り組みの具体策は鉄道の自動運転です。2024年3月に踏切のある在来線としては全国で初めて自動運転を導入し、これで従来の運転士の仕事を車掌が兼務できるようなりました。運転士の育成には8カ月を要し、運転士の希望者も減少しています。人口減少の中で、鉄道事業の持続可能性を高めるための取り組みです。
実はこの自動運転開始の8年前、私は鉄道事業本部長として「会社を去るまでに実現させる」と意気込んで、先頭に立って開発を進めていました。過去の常識を打ち破る、こうした取り組みが勢いづいたのはコロナの影響だと思います。「挑戦を続けよう」と私は訴え、社員たちは必死で過去の常識を変えていきました。これは将来のJR九州グループの大きなアドバンテージになると確信しています。
地域に合ったモビリティサービスのあり方を模索
人口減少が加速する地域を走るローカル線を今後どうするか──。避けては通れない課題です。今年4月に熊本県と肥薩線(八代~人吉間)の鉄道での復旧に関する最終合意書を取り交わしましたが、復旧へ向けて私は、「鉄道での復旧には、日常利用の創出が不可欠である」と申し上げ、積極的に利用促進の取り組みを行っていただけることになりました。持続可能な交通体系とは何かを徹底的に話し合えば、自ずとそれぞれの地域に合ったモビリティサービスのあり方が見えてきます。当社には日田彦山線でBRT(バス高速輸送システム)転換の実績もあります。引き続き、地域の皆さまと存廃を前提としない対話を尽くし、ともに持続可能な未来を築いていきます。
環境対応は「保全」と「ビジネス」の両面から
九州の豊かな自然は地域の大きな魅力である一方、時として自然災害による影響を受けることがあります。このため、環境課題への対応に力を入れることは、安全・安心な鉄道事業を担うために不可欠です。これらを踏まえ、「JR九州グループ環境ビジョン2050」を掲げ、気候変動対応をはじめとする環境課題に対して、当社グループとしてできることを着実に推進してまいります。
また、環境に関する取り組みはビジネス創出の機会としても重視しています。現在注力しているのは再生可能エネルギーの領域であり、今年3月にはソーラー発電事業者と連携して、九州エリアの中小型太陽光発電所の取得・集約を進めています。これにより、長期的な安定運営を実現するとともに、地域のカーボンニュートラル達成に寄与する社会課題解決型ビジネスに挑戦しています。また、将来的に想定される太陽光パネルの大量廃棄に対応するため、パネルリサイクル事業の検討も進めております。

ステークホルダーの皆さまへ
高速船の問題に関しステークホルダーの皆さまには大変ご心配をおかけしました。グループ全体のリスク管理体制を見直しましたが、安全は当社グループのすべての事業で最優先することが使命であり、そのうえで企業価値向上、持続可能な成長を目指してまいります。新たな経営理念には「我々もこれから挑戦を続けていきますので、ステークホルダーの皆さまもともに九州の元気をつくっていきましょう」という念いも込めています。社会に必要とされる企業であり続けるために、「わたしたちの夢」の実現に向けて責任を持って取り組んでいきます。

Contents